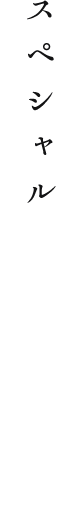-
あいづせんそう
会津戦争
会津藩と維新政府軍との間に生じた戊辰戦争第四の戦役。
会津藩は降伏したが、維新前に京都守護職につき維新志士を取り締まっていたこともあり、藩の人々はこの後長い年月に渡って政府から弾圧を受けることになった。 -
あへん
阿片
ケシの実から採取できる乳液状の樹液を乾燥させて作る麻薬。
恐ろしいまでの禁断症状を引き起こすため、一国を滅ぼしかねない凶薬として強く禁じられていた。 -
あまかけるりゅうのひらめき
天翔龍閃
飛天御剣流の奥義で最強の技。神速を超える超神速の抜刀術。 -
いけだやじけん
池田屋事件
元治元年(1864年)6月に、京都三条の旅館『池田屋』に潜伏していた維新志士を新撰組が強襲した事件。
その志士たちは、京都へ火を放つことでその混乱に乗じ、幕府要人の暗殺と天皇を長州へ移送を企んでいたとされる。
新撰組は計画を未然に防いだとして、知名度を一躍高めた。 -
いしんさんけつ
維新三傑
明治維新での改革や維新後の国家建設を先導した、西郷隆盛・木戸孝允・大久保利通の三人の志士を指す。 -
いしんしし
維新志士
幕末期に改革を目指した武士たちの総称。しばしば薩摩(鹿児島)、長州(山口)、土佐(高知)、肥前(佐賀)、その他(水戸、福岡など)と、出身地別に5つに大別される。
中でも薩摩は警察、長州は軍部内で絶対的権力を誇り、明治の官憲に二大勢力として長く君臨した。 -
いちのひけんほむらだま
壱の秘剣『焔霊』
志々雄の技の一つ。 -
うえのせんそう
上野戦争
戊辰戦争の一つ。慶応4年(1868年)に、江戸上野で行われた、彰義隊ら旧幕府軍と薩摩・長州を中心とした新政府軍との戦い。 -
うきあしおとし
浮足落とし
長岡幹雄の必殺技。相手の足元を狙って地を這うように刀を切り払う技。 -
えぞうししんぶん
絵草紙新聞
事件を描いた錦絵とその錦絵を説明する文章で構成された、視覚的要素の強い一般大衆向けのニュース媒体。 -
えんさつごうこうこん
円殺轟鉤棍
柏崎念至の技。密着状態から回転させて威力をあげた鉤棍を叩きつける。 -
おうかせいさく
欧化政策
欧米の文化を取り入れ日本が文明国であることを示し、不平等条約の改正を目指した政策。 -
おにわばんしゅう
御庭番衆
最強の隠密集団。江戸時代に活躍した密偵、間者の一種であり、中でも将軍直属の諜報機関として、他のどの隠密より戦闘術に長けた者によって構成されている。
現代では忍び、忍者と呼ばれることが多い。 -
おんみょうこうさ
陰陽交叉
四乃森蒼紫の技。一刀目の峰に、もう一刀目の刃を叩きつけることで押し切る。
-
かいてんけんぶ
回天剣舞
四乃森蒼紫の技。緩急自在の流水の動きによって繰り出される、拳法の動きと小太刀の技を複合した実践剣舞。 -
かえんといき
火炎吐息
御庭番衆・火男の技。胃に仕込んだ油袋と火打ち石の歯を使って火炎を起こす技。 -
がとつ
牙突
斎藤一の技。腰を落とした姿勢から刀を水平にして切っ先を相手に向け、峰に軽く右手を添える左片手平刺突の構えから、一気に間合いを詰めて突進し、相手を貫く。 -
がとりんぐがん
ガトリングガン
1861年、アメリカの医師、ガトリングによって開発された兵器。
日本では越後長岡藩が購入。北越戦争において、官軍の大きな脅威となった。 -
かみやかっしんりゅう
神谷活心流
“人を活かす剣”である活人剣を志す剣術流派。神谷薫が師範代を務める。 -
がりゅうおろち
我流『大蛇』
張の技の一つ。薄い刃を大蛇のようにうならせ攻撃する。 -
がりゅうどくが
我流『毒牙』
張の技の一つ。蜷局をまいた蛇のように薄い刃を渦巻状にし、剣先を上空に向かわせ攻撃する。 -
がりゅうとぐろ
我流『蜷局』
張の技の一つ。蛇が獲物を絞め殺すときのように、薄い刃を巻き付けて攻撃する。 -
かんさつとびくない
貫殺飛苦無
巻町操の技。複数の苦無を一度に相手へ投げつける。 -
かんりこうきょざい
官吏抗拒罪
官吏(役人や官人)に脅迫や暴行を加え、職務を妨害すること。 -
きおいざかのへん
紀尾井坂の変
明治11年(1878年)5月14日、内務卿・大久保利通が暗殺された大事件。
紀尾井坂は、現在の東京都千代田区にある坂で、紀州徳川家・尾張徳川家・彦根藩井伊家にちなんでよばれるようになった。 -
きざみうち
刻み打ち
尖角の技の一つ。速さと剛力を活かし、握り懐剣を連続で繰り出す攻撃。 -
ぎゅうなべ
牛鍋
現代で言うところの「すき焼き」。
庶民が口にできる西洋料理の代表的な食べ物で、人気を博した。 -
きょうそうしゅう
梟爪衆
志々雄配下の兵隊で、夜目が効く者を選りすぐった夜襲専用の隠密部隊。 -
きょうとたんさくがた
京都探索方
幕末に京都が動乱の中心地になると予想した先代の御庭番衆御頭によって、御庭番衆独自の情報収集網をつくるために配置した役職。
柏崎念至こと『翁』が担い、拠点として葵屋を開いた。 -
くずりゅうせん
九頭龍閃
飛天御剣流の神速を最大に発動することで九つの斬撃を同時に打ち込む技。
斬撃全てが一撃必殺の威力を有すると同時に突進術でもある故に、防ぎ切ることも回避し切ることも絶対不可能とされている。
もともとは奥義伝授の過程の中で生まれた試験としての技であり、師の放つ九頭龍閃を破ることが出来れば奥義の伝授が完了する。 -
ぐぜ
救世
仏教用語で、世の人々を苦しみの中から救うこと。 -
くだやり
管槍
持ち手に管を通すことで、より俊敏な突きを繰り出せる特別な槍。 -
くものす
蜘蛛の巣
武田観柳が高荷恵に作らせていた阿片の通称。
特別な精製法によって従来の半分の原料で作れ、依存性は通常の2倍にもなる。 -
けちょうげり
怪鳥蹴り
巻町操の技。飛び蹴り。 -
こだち
小太刀
刀と脇差の中間の剣。刀より短い分、攻撃力に劣るが軽量で小回りが利くため、防御力が非常に高い。 -
ころり
虎狼痢
コレラという感染症の別称。「ころりと死ぬ」ことから。
激しい下痢や嘔吐といった症状を起こし、江戸後期の医療技術では極めて高い死亡率であった。
-
さかさちゅうくうのうとう
逆中空納刀
鞘を上空に飛ばした後、真上に向けた刀を鞘に収める技。。 -
さかばとう
逆刃刀
刃と峰が逆さになった刀。 -
ざんばとう
斬馬刀
馬ごと敵を斬るための剣。古いものなので切れ味は無く、左之助は叩き潰すように使用する。 -
しぞく
士族
明治維新後、武士階級だった者に与えられた身分。 -
じって
十手
江戸時代に罪人を捕まえる役人が使用した道具。
鉄製の棒で、下部に鉤がついている。 -
しみんびょうどう
四民平等
平民も苗字を名乗ることが認められるなど、士農工商の身分差別を廃止しようとする考え方。 -
しょうぎたい
彰義隊
徳川幕府15代将軍・徳川慶喜の警護を目的として結成された旧幕府側の部隊。
江戸開城後も新政府軍と衝突を繰り返していたが、上野戦争にて壊滅した。 -
じゆうみんけんうんどう
自由民権運動
板垣退助らの「民撰議院設立建白書」の提出をきっかけににおこった政治運動。
国会開設や憲法改正、国民の政治参加などを主張した。 -
しんうち
真打
御神刀を打つ時、ひと振りでなく、あらかじめふた振り、もしくは複数打つのが通例で、その中で最もよくできたひと振りを『真打』といって神に捧げた。
その残りを『影打』といい、死蔵したり人に譲ったりする。
剣心の逆刃刀は、新井赤空から直接渡されたものが『影打』で、白山神社に奉納されていたものが『真打』であった。 -
しんげつむら
新月村
東海道の十二番目の宿場である沼津宿から少し離れた人口五十人ほどの集落。
沼津宿は現在の静岡県沼津市大手町周辺にあたる。 -
しんけんのかまえ
『信剣』の構え
正眼から両腕を伸ばし、切先を水平に相手の眉間に付けるように構える。
相手の如何なる変化にも即対応できる、古流剣術に見られる防御堅固の構え。 -
しんこりゅう
真古流
古流剣術の再興を目指す剣客集団。石動雷十太はその集団の頭目。 -
しんせんぐみ
新撰組
倒幕を目論む維新志士を鎮圧すべく、幕府によって集められた組織。
実力派揃いの剣客が集った。 -
しんせんぐみたいき
新撰組隊規
新撰組副長・土方歳三が内部統制のために考案したとされる規律。
全五箇条からなり、一つでも破ったものは切腹に処されたと言われている。 -
しんのいっぽう
心の一方
またの名を「居縮の術」。二階堂平法の奥義。暗示をかけ、金縛りのように身体の自由を奪う。 -
しんわんのじゅつ
伸腕の術
御庭番衆・般若が使う術。両腕に施された横縞の入れ墨によって相手に目の錯覚を起こさせ、目測を見誤らせる術。 -
すんてつ
寸鉄
手のひらに収まるほど小さい隠し武器。 -
せきほうたい
赤報隊
慶応四年、鳥羽・伏見の戦いの直後に民衆・在野で結成された草莽部隊。
官軍(維新軍)に先行して沿道諸藩を探り、また協力を促す「嚮導先鋒」の役割を担った。 -
せんげきらせんびょう
穿撃螺旋鏢
御庭番衆・癋見の技。螺旋状に溝が掘られた鉄製の鏢を指で弾き撃つ、貫通力の高い技。 -
せんねんおうき
千年王城
京都のこと。近畿地方中央の盆地に位置する都市で、美術工芸の中心地であると共に、日本仏教の中心地でもあり、794年の遷都以来、千年あまりのあいだ都であったことが由来。 -
そうりゅうせん
双龍閃
飛天御剣流の技のひとつ。剣と鞘を使った二段抜刀術。 -
そうりゅうせん・いかづち
双龍閃・雷
飛天御剣流の技「双龍閃」の派生技。鞘打ちから剣撃につなげる二段抜刀術。
-
ちょう・にんげんどきゅう
超・人間弩弓
尖角の奥義。地面に握り懐剣を突き立て身体を固定し、自らを弩弓の矢のように発射する技。
脚だけでなく腕の力も使い、全身の筋力を推進力に変えた頭突きを繰り出し相手を串刺しにする。 -
デストルニジャドール・サーベル・エスティーロ
エスピラール・ロタシオンの技。身体を極限まで捻ることで生み出される回転の力を利用し、最大の力を得て繰り出すサーベル術。 -
テンペスター・インフィエールノ
デストルニジャドール・サーベル・エスティーロの技の一つ。
トルメンタ・インフィエールノを連続して繰り出す突き技。 -
とうかいどう
東海道
江戸時代からある五街道の一つで、東京日本橋から京都三条大橋までを結んでいる。今の距離で約492㎞ある。 -
とうぎさつ
当義殺
正当防衛のこと。 -
とばふしみのたたかい
鳥羽伏見の戦い
1868年、京都南郊の鳥羽・伏見において新政府側と旧幕府側との間で展開され、戊辰戦争の発端となった戦い。 -
とりもの
捕り物
警察が罪人を取り押さえること。 -
トルナード・インフィエールノ
デストルニジャドール・サーベル・エスティーロの最強最速の奥義。
全身を捻り上げ、その回転力をサーベルに上乗せして繰り出す最強最速の突き技。 -
トルメンタ・インフィエールノ
デストルニジャドール・サーベル・エスティーロの技の一つ。
サーベルを捻ることで生み出される回転力を利用した突き技。 -
トンファー
鉤棍
柏崎念至の武器。鋼鉄で作られており、刀では斬れない。
-
なかせんどう
中山道
江戸時代からある五街道の一つで、東京日本橋から京都三条大橋までを結んでいる。今の距離で約526㎞ある。
東海道が南回りであるのに対し、中山道は北回りの道で、草津宿からは東海道と合流する。 -
にかいどうへいほう
二階堂平法
一文字、八文字、十文字の三段の型で構成される剣術。
一、八、十の字画で「平」を成すことから平法と呼ばれている。 -
にしきえ
錦絵
浮世絵の一種で、色鮮やかな絵で明治の文化や風俗を伝えた。 -
にんげんどきゅう
人間弩弓
尖角の技の一つ。鍛え上げた肉体を活かし脚の力のみで頭から一直線に飛び込む攻撃。 -
のろし
狼煙
遠方への情報伝達のために、薪や火薬などを使用して高く上げる煙。
-
はいしゃとう
背車刀
背後で刀を持ち替え、予測不能な方向から斬撃を繰り出す技術。 -
はいとうれい
廃刀令
明治9年に布告された法令。武士や庶民らの帯刀を禁じた。 -
はいぶつきしゃく
廃仏毀釈
仏教を排斥しようとする政策や行動のことで、一般的には明治元年(1868年)に明治政府が神仏分離令をきっかけに行われたものを示す。
当時の明治政府は、神社から仏教の要素を排除し、神道国教化する方針だったが、実際には、古い慣習からの転換期も相まって全国的に極端な廃仏運動が展開されていた。 -
はかいそう
破戒僧
不殺生、不淫など、仏の定めた戒めを破って恥じない、堕落した僧のこと。 -
はくじんのたち
薄刃乃太刀
刀匠・新井赤空が鍛刀した後期型殺人奇剣。
刃の強度を保ったまま、可能な限り薄く鍛えた異形の太刀。
剣先をわずかに重くすることによって、手首の微妙な返しをそのまま刀の軌道に伝え操ることが出来る。 -
はたもと
旗本
江戸幕府将軍直属の家臣団のなかで、江戸幕府将軍に拝謁できる御目見が許された武士の身分。江戸幕府に直属する常備軍の中核となった人々であった。 -
ばっとうじゅつ
抜刀術
刀剣の刃を鞘内で走らせ、抜き放つことによって剣速を2倍、3倍に加速させる技術。
相手に攻撃の間を与えずに斬り伏せる、一撃必殺の大技。 -
ひけんいづな
秘剣『飯綱』
石動雷十太が古流剣術の秘伝書から会得した秘剣。
真空の刃を利用し、剣の斬撃力を増大させる技。 -
ひけんとびいづな
秘剣『飛飯綱』
秘剣『飯綱』の技の一つ。
真空の刃を飛ばし、間合いの外にいる相手にも攻撃できる遠距離技。 -
ひてんみつるぎりゅう
飛天御剣流
一対多数の斬り合いを得意とする神速の殺人剣。人斬り抜刀斎が振るう剣術流派。 -
ひときりばっとうさい
人斬り抜刀斎
圧倒的強さで幕末の動乱期に暗躍した、伝説の剣客の呼び名。 -
ひょうきのじゅつ
憑鬼の術
心の一方の影技。自分自身に強力な暗示をかけ、潜在するすべての力を発揮する技。 -
ひりゅうせん
飛龍閃
飛天御剣流の技の一つ。納刀した刀を回転しながら弾き飛ばし相手に命中させ、さらに刀を鞘に納める勢いを利用して追い打ちをかける技。 -
ふたえのきわみ
二重の極み
拳を立てて石に第一撃を加え、拳を折って第二撃を入れる。
第一撃の衝撃が石の抵抗とぶつかった瞬間に第二撃を入れることで、第二撃目の衝撃は、抵抗を受けることなく完全に伝わり、石を粉砕することができる破壊の極意。 -
ぶんめいかいか
文明開化
明治時代、日本に西洋の文化や習慣を取り入れたことで、急速に近代化が進んだ現象。
-
まといいづな
纏飯綱
秘剣『飯綱』の技の一つ。刀そのものに真空の刃をまとわせて相手に斬りつける技。真剣で放てばダイヤモンドでも真っ二つにするすさまじい切れ味を誇る。 -
めいじいしん
明治維新
江戸時代から明治時代への政治的革命のこと。武家社会は終わりを告げ、武士は様々な特権を手放すこととなった。 -
もくほう
木砲
幕末まで使用されていた簡易大砲。樫の木の砲身から撃ち出される粘土玉の威力は、至近距離なら普通の大砲にもひけをとらない。 -
もどしぎり
戻し切り
切り口の組織を全く潰すことなく切ることによって、再び元通りに出来てしまうという、名刀と達人の腕が揃って初めてできる高度な技。
-
りゅうかんせん
龍巻閃
飛天御剣流の技の一つ。身体を回転させ、相手の背後に回り込んで攻撃する技。 -
りゅうかんせんつむじ
龍巻閃・『旋』
飛天御剣流の技「龍巻閃」の派生技。 -
りゅうこうせん
龍咬閃
飛天御剣流の技の一つ。飛天御剣流唯一の徒手空拳技。 -
りゅうしょうせん
龍翔閃
飛天御剣流の技の一つ。本来は、峰を右手で支えて下から飛び上がり、刃を立てて斬り上げる技だが、剣心は相手の顎を刀の腹で打ち上げている。 -
りゅうそうせん
龍巣閃
飛天御剣流の技のひとつ。全身の急所を高速・連続で斬りつける。 -
りゅうついせん
龍槌閃
飛天御剣流の技のひとつ。空中に高く飛び上がり、落下重力を利用して相手の頭上から一気に刀を振り下ろす。 -
るろうに
流浪人
緋村剣心が自らを表した言葉。流浪人(るろうにん)。あてもなく放浪する人。 -
れんばとう
連刃刀
刀匠・新井赤空が鍛刀した初期の殺人剣。
二振りの刀を合体させると、一つの柄から二つの刃が短い間隔で並んでいる。
同じ傷が間隔短く2つ生じるため、明治時代の医療技術では、傷口の縫合が難しく、本来であれば致命傷に至らない傷であっても、手当てができないことによって傷口を腐らせ、死に至らしめるという。